大切な人への感謝の気持ちや、お世話になっている方へのご挨拶として欠かせない「手土産」。
せっかく心を込めて選んだ品物も、渡し方一つで相手に与える印象は大きく変わってしまいます。
「どのタイミングで渡せばいいの?」
「紙袋のまま渡してもいいの?」
「『つまらないものですが』って言っても大丈夫?」
――手土産を渡す際には、意外と多くの人が迷いや不安を感じるものです。
この記事では、そんな悩みを解決し、あなたの真心をよりスマートに伝えるための「手土産の渡し方」を徹底解説します。
訪問先での最適なタイミングから、美しい所作、そして相手に心地よく受け取ってもらえる一言フレーズまで、具体的なシーンを交えながらご紹介。
さらに、ついつい使いがちな「つまらないものですが」という言葉の言い換え表現や、受け取る側のマナーにも触れていきます。
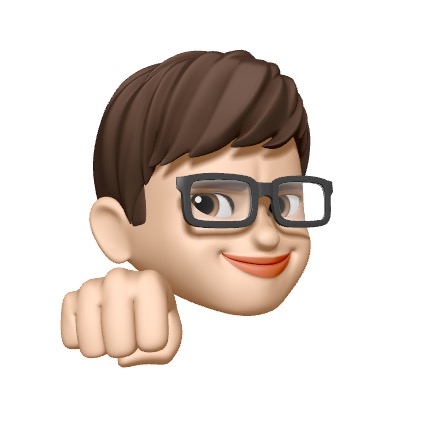
この記事を読めば、あなたも手土産マスター!自信を持って、そして相手に喜ばれる手土産のコミュニケーション術を身につけましょう。
手土産を渡す前の心得 ~準備で差がつく第一歩~


スマートな手土産の渡し方は、実は訪問前から始まっています。
相手に喜ばれ、かつ失礼のない手土産にするための準備と心構えを確認しましょう。
相手を想う品物選びが基本(おさらい)
手土産の品物選びは、相手の好みや家族構成、アレルギーの有無、健康状態などを考慮することが最も大切です。
また、訪問先の状況(冷蔵庫のスペース、日持ちの必要性など)も考えられると、より一層相手への配慮が伝わります。
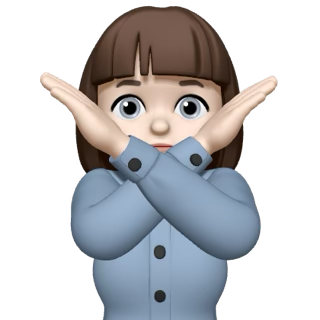
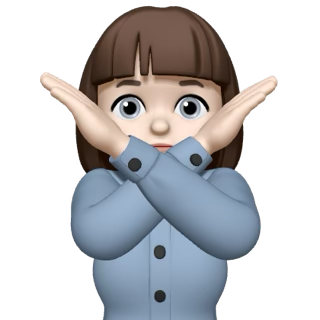

高価すぎるものはかえって相手に気を使わせてしまうこともあるため、金額の相場も意識しましょう。
(品物選びの詳細については、関連記事「「センスいいね!」と言われる手土産選びの基本ルール – 失敗しないための5つのポイント」もご参照ください。)


清潔感のある持ち運びで印象アップ
選んだ手土産は、相手に渡す瞬間まで大切に扱いましょう。
包装の確認
購入時に包装が崩れたり汚れたりしていないか確認します。
のし紙が破れたり汚れたりしないよう注意しましょう。
(「のし」の詳細については、関連記事「【意外と知らない?】手土産の「のし」完全ガイド – 種類・書き方・注意点」もご参照ください。)
持ち運び方
特にケーキや生菓子など形が崩れやすいものは、水平に保てるように工夫し、丁寧に持ち運びます。
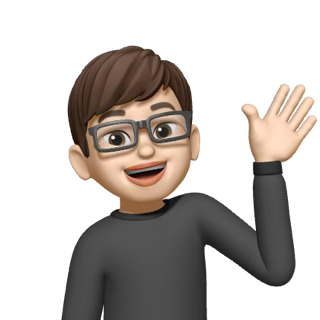
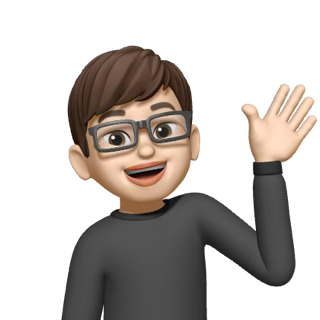

夏場は保冷剤を添えるなどの配慮も忘れずに!
紙袋も清潔に
手土産を入れる紙袋も、汚れていたりシワが寄っていたりすると残念な印象に。
できるだけ綺麗で、品物の格に合ったものを選びましょう。
訪問先への到着時間と心構え


約束の時間に余裕をもって
約束の時間に遅れるのは論外ですが、早すぎる到着も相手の準備を急かしてしまう可能性があります。
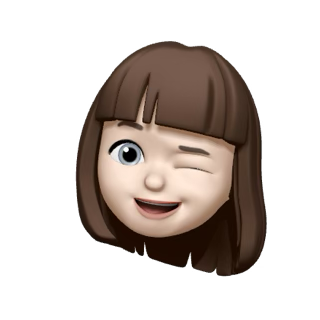
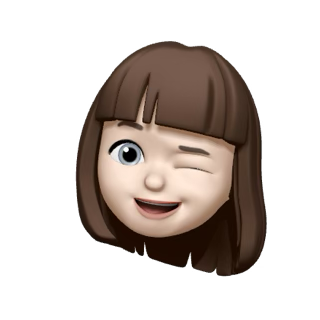

5分前~時間通りに到着するのが理想的です。
身だしなみを整える
訪問先に入る前に、服装の乱れや髪型などを軽くチェックしましょう。
清潔感のある身だしなみは、相手への敬意の表れです。
いつ渡すのが正解?手土産を渡す最適なタイミング


手土産を渡すタイミングは、訪問先の状況や目的によって異なります。
最適なタイミングを見極めることが、スマートな印象を与える鍵となります。
個人宅への訪問の場合
基本は部屋に通されてから
玄関先で慌ただしく渡すのは避けましょう。
一般的には、部屋に通され、挨拶を済ませて落ち着いたタイミングで渡すのがマナーです。
席に着く前か、着席してすぐが良いでしょう。
冷蔵・冷凍品の場合
アイスクリームや生ものなど、すぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れる必要がある場合は、
玄関先で「こちらは冷蔵(冷凍)品ですので、お預けしてもよろしいでしょうか」と一言添えて、先に渡しても構いません。
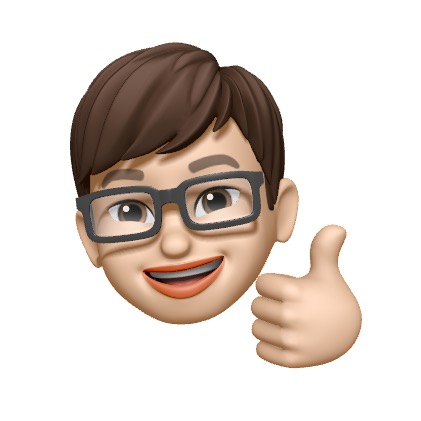
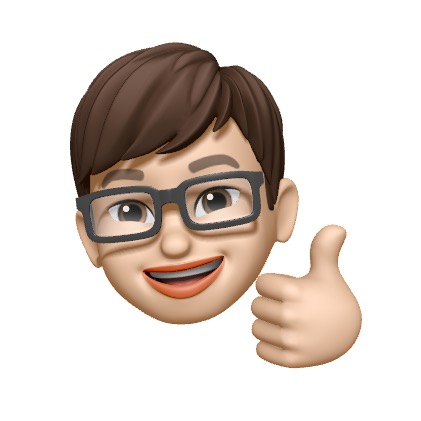

その際も、改めて部屋で挨拶を済ませた後に、手土産について触れると丁寧です。
食事やお茶に招かれた場合
他のゲストがいる場合や、皆でいただくことを想定している場合は、食事が始まる前に渡すと、相手も準備がしやすくなります。
「こちら、よろしければ皆さんで召し上がってください」などと声をかけましょう。
お開きの際
個別に渡したい場合や、相手の状況を見て渡すタイミングを逃してしまった場合は、帰り際に「本日はありがとうございました。こちら、ささやかですが…」と渡すこともできます。
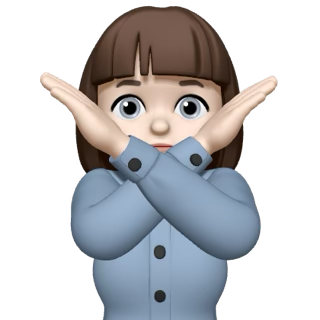
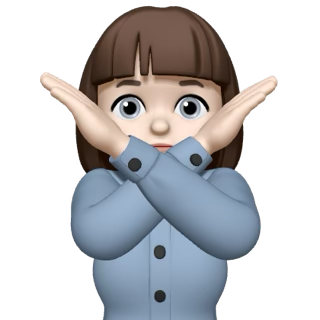

ただし、渡しそびれて持ち帰ることのないように注意しましょう。
ビジネスシーンでの訪問の場合
挨拶の後、本題に入る前
応接室や会議室に通され、担当者と挨拶を交わした後、名刺交換などがあればそれが済んでから、本題に入る前に渡すのが一般的です。
「本日はお時間をいただきありがとうございます。こちら、よろしければ皆様で召し上がってください」などの言葉を添えましょう。
会食の場合
開始前であれば、席に着いて落ち着いたタイミングで、相手に邪魔にならないように渡します。
タイミングを逃した場合や、相手が荷物になることを気遣う場合は、お開きの際に「本日はありがとうございました。こちら、お土産にどうぞ」と渡すこともあります。
大人数への手土産(部署宛など)の場合は、代表者に渡すか担当者に「皆様でどうぞ」と伝えて渡します。
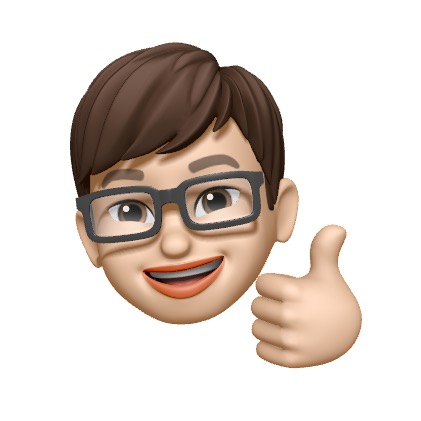
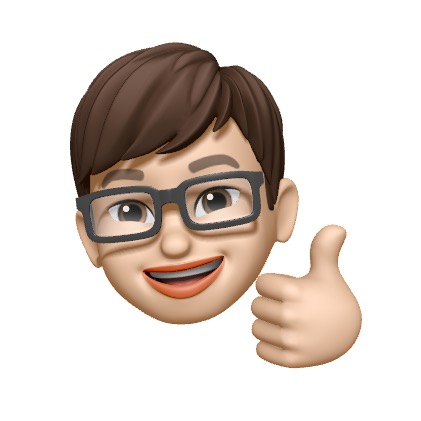

個包装で分けやすいものが喜ばれます。
お祝いやお礼など、目的が明確な場合
結婚祝いや出産祝い、お中元やお歳暮、お礼など、手土産の目的がはっきりしている場合は、訪問して挨拶を済ませた後、比較的早いタイミングで渡すのが自然です。
「この度はおめでとうございます」「先日はありがとうございました」といった祝福やお礼の言葉と共に渡しましょう。
避けるべきタイミング
電話中や他の来客対応中など、相手が取り込んでいる時、相手が忙しそうな時に渡すのは避けましょう。
コートを脱いだり、靴を揃えたりするようなバタバタした状況の中、玄関先で慌ただしく渡すのはスマートではありません。
(ただし、冷蔵品・冷凍品などは例外です。)
また、会話の流れを遮ったり、食事の手を止めさせたりするようなタイミングは避けましょう。
美しい所作で渡す ~スマートな手渡しテクニック~


手土産を渡す際の所作は、相手に与える印象を大きく左右します。



丁寧で美しい渡し方をマスターしましょう。
紙袋の扱い方 ~出すのが基本、例外も~
紙袋から出して渡すのがマナー
手土産は、持参した紙袋から取り出して渡すのが基本です。
紙袋はあくまで持ち運び用のものであり、そのまま渡すのは「相手に手間をかけさせる」「埃がついているかもしれない」という解釈から、失礼にあたるとされています。
紙袋のたたみ方と持ち帰り
1. 品物を紙袋から取り出します。
2. 紙袋は軽くたたみ、持ち手を手前にして置くか、自分のバッグにしまいます。
3. 相手に「紙袋はこちらで処分いたしましょうか?」と尋ねるのも一つの配慮ですが、基本的には自分で持ち帰ります。特にブランドのロゴが入った紙袋などは、相手が処分に困ることもあるため、持ち帰るのが無難です。
例外的に紙袋ごと渡す場合
- 公園や駅など、品物を直接置く場所がない屋外で渡す場合。
- ホールケーキやお酒の瓶など、品物が大きく持ち運びにくく、紙袋があった方が相手が持ち帰りやすい場合。
- 相手が持ち帰る際に、ホコリや汚れるのを防ぎたい場合。
- 「そのままで結構ですよ」と相手からリクエストがあった場合。
その際の言葉添え
- 「紙袋のままで失礼いたしますが、こちらの方がお持ち帰りやすいかと思いまして」
- 「こちら、袋ごとで恐縮ですが、どうぞ」
などと一言添えましょう。
品物の向きは相手への心遣い
品物の正面(包装紙の柄が一番きれいに見える面や、のし紙の文字が読める向き)を相手に向けて渡します。
自分の方に正面を向けて持ってきた品物を、渡す直前に向きを変え、時計回りに回転させて相手に正面を向けるのが丁寧な所作とされています。
のしがある場合は、のし紙の表書きや名前が相手からはっきりと読める向きにして渡します。
丁寧な渡し方 ~両手で、敬意を込めて~


品物は、胸の高さあたりで両手で持って差し出すのが基本です。
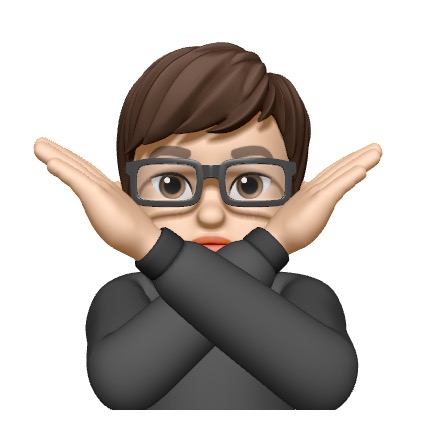
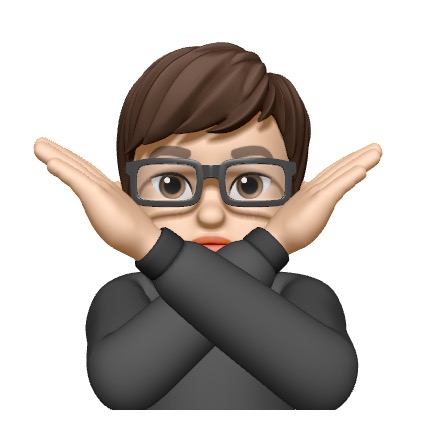

片手で渡すのは失礼にあたります。
テーブル越しはNG
テーブル越しに手を伸ばして渡すのは避けましょう。
可能な限り相手のそばに移動し、直接手渡します。
それが難しい場合は、「こちらから失礼いたします」と一言断ってから渡すか、一旦テーブルの相手に近い場所に丁寧に置き、「どうぞお取りください」と促します。
床に直接置かない
訪問先で手土産を一時的に置く必要がある場合でも、床に直接置くのは避けましょう。
自分のバッグの上や、サイドテーブルなどがあれば利用します。もし置く場所がなければ、自分の膝の上に置くか、手に持ったままにします。
心に響く!添える一言フレーズ集 ~言葉で伝える感謝の気持ち~
手土産を渡す際には、心を込めた一言を添えることで、より相手に気持ちが伝わります。シーンや相手に合わせたフレーズを使い分けましょう。
基本の万能フレーズ
- 「心ばかりの品ですが、どうぞお納めください。」
- 「ささやかですが、感謝の気持ちです。お受け取りください。」
- 「こちら、皆さんで召し上がってください。」
- 「お口に合うと嬉しいです。」
- 「ほんの気持ちですが、どうぞ。」
「つまらないものですが」はもう古い?謙遜表現のアップデート
かつては定番だった「つまらないものですが」という謙遜の言葉。
これは「立派なものではないですが」という意味合いで使われていましたが、現代では「本当につまらないものをくれるのか」とネガティブに捉えられたり、卑屈な印象を与えたりする可能性も指摘されています。
もちろん、相手や状況によっては問題ない場合もありますが、よりポジティブで洗練された言い換え表現を使うのがおすすめです。
「つまらないものですが」の言い換え例
より丁寧な謙遜表現
- 「お口汚しかもしれませんが、お納めください。」(主に食べ物の場合)
- 「心ばかりの品ではございますが、お受け取りいただけますと幸いです。」
- 「粗品ではございますが、どうぞ。」(ビジネスシーンで使われることも)
相手への配慮を示す表現
- 「〇〇(相手の名前)さんがお好きだと伺いましたので、こちらをお持ちしました。」
- 「評判が良いと聞きましたので、よろしければお試しください。」
- 「少しですが、お近づきのしるしに。」(初対面の場合など)
- 「旅先で見つけた美味しいものですので、おすそ分けです。」
謙遜しすぎるとかえって相手に気を遣わせてしまうこともあります。
感謝の気持ちや相手を思う気持ちを素直に表現する言葉を選ぶと良いでしょう。
シーン別・気の利いた一言フレーズ集
個人宅訪問時
「本日はお招きいただきありがとうございます。こちら、ほんの気持ちですが、皆さんで召し上がってください。」
「(子供がいる場合)お子さんたちにも喜んでもらえると嬉しいです。」
「近所で評判のお菓子です。お口に合いますでしょうか。」
ビジネスシーン
「本日は貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございます。こちら、弊社からの心ばかりの品でございます。皆様でどうぞ。」
「いつも大変お世話になっております。日頃の感謝の気持ちです。」
「(季節に合わせて)季節のご挨拶にお持ちいたしました。」
お礼を伝える時
「先日は大変お世話になり、ありがとうございました。こちら、ささやかですが感謝のしるしです。」
「おかげさまで助かりました。ほんの気持ちですが、お受け取りください。」
お祝いの席で
「この度は誠におめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。ささやかですが、お祝いの品です。」
「(出産祝いなど)健やかなご成長をお祈りしております。こちらは、ママへの応援の気持ちも込めて。」
相手の好みを考えて選んだ場合
「〇〇さんが△△がお好きだと伺ったので、探してきました。気に入っていただけると嬉しいです。」
「以前、〇〇がお好きだとおっしゃっていたのを覚えておりましたので。」
話題の品や珍しい品の場合
「最近話題の〇〇です。ぜひ一度召し上がってみてください。」
「なかなか手に入らないと聞いたので、お持ちしました。」
体調を気遣う場合
「お身体に優しいと聞きましたので、こちらを選んでみました。」
「〇〇は使っておりませんので、安心してお召し上がりいただけるかと思います。」(アレルギーに配慮)
日持ちしないものを渡す場合
「本日中にお召し上がりいただきたいのですが、よろしいでしょうか。」
「あまり日持ちがしないので、お早めにお口にしていただけると嬉しいです。」
渡す相手への配慮が伝わるプラスワンフレーズ
アレルギーや食事制限がある方へ
「こちらは〇〇(アレルゲンなど)は使用しておりませんので、安心してお召し上がりください。」
「甘さ控えめなので、〇〇さんにもお召し上がりやすいかと思います。」
賞味期限について
「少し賞味期限が短いのですが、お早めにお召し上がりください。」
「こちらは日持ちがしますので、ごゆっくりどうぞ。」
食べ方や楽しみ方の提案
「冷やして召し上がると、より一層美味しいそうです。」
「このお菓子は、〇〇(飲み物など)とよく合うと聞きました。」
手土産を受け取る側のマナーも心得ておこう
自分が手土産を受け取る側の立場になることもあります。
その際のスマートな対応も知っておくと、お互いに気持ちの良いコミュニケーションが取れます。
感謝の言葉をはっきりと
手土産を受け取ったら、まず相手の目を見て、笑顔で「ありがとうございます」と感謝の気持ちをはっきりと伝えましょう。
「わざわざありがとうございます」「お気遣いいただき、恐縮です」といった言葉を添えるのも良いでしょう。
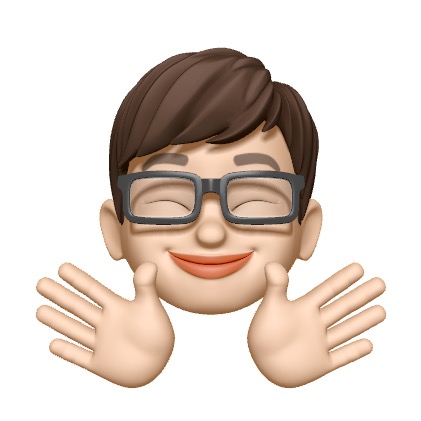
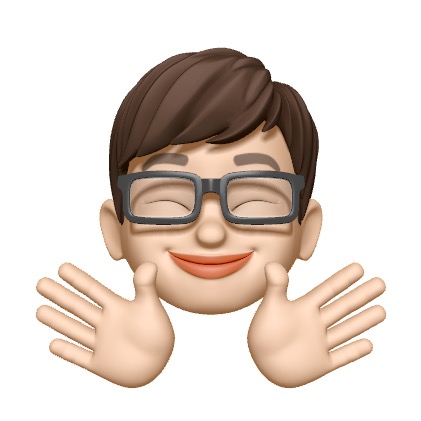

声のトーンは明るく、感謝の気持ちが伝わるように心がけてください。
両手で受け取る
手土産は、両手を添えて丁寧に受け取るのがマナーです。
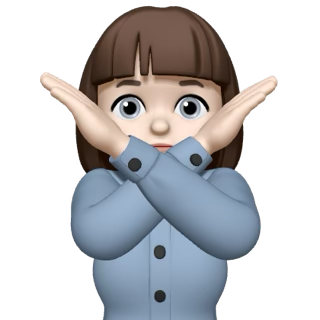
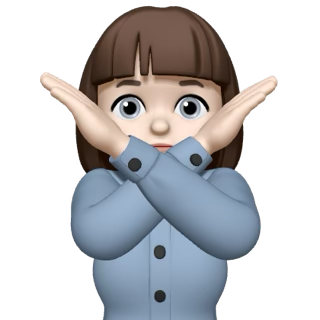

片手で受け取るのは、少しぞんざいな印象を与えてしまう可能性があります。
もし、大きな品物で両手で支えきれない場合は、片手を添えるだけでも印象が違います。
相手への敬意を示す気持ちを表しましょう。
すぐに開けるべき?
基本的には、その場で開けて喜びや感謝を伝えるのが喜ばれます。
「わあ、素敵ですね!」「美味しそうですね、ありがとうございます」など。
ただし、他の来客が大勢いる場合や、すぐにしまわなければならない生ものなどの場合は、無理にその場で開けなくても構いません。
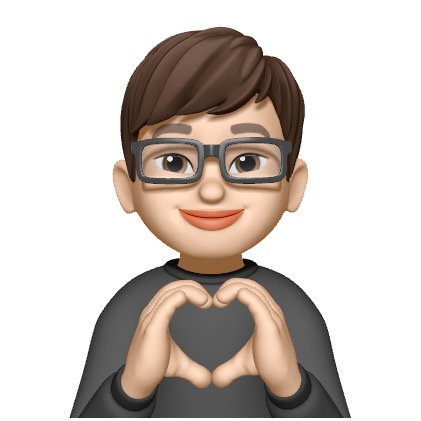
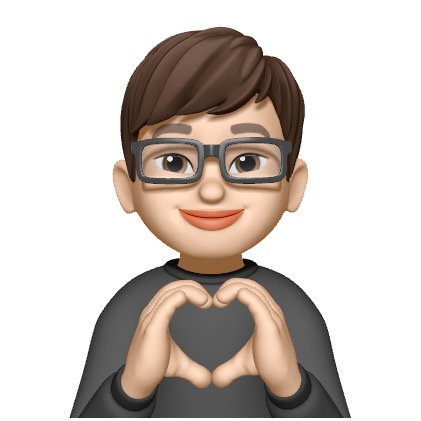

「後ほどゆっくり拝見(頂戴)いたします」と伝えましょう。
ビジネスシーンでは、その場で開けないのが一般的ですが、相手から「どうぞ開けてみてください」と促された場合は、感謝して開けても良いでしょう。
いただいた品物を丁寧に扱う
いただいた品物は、感謝の気持ちを込めて丁寧に扱いましょう。
持ち帰る際には、袋が破れたり、中身が崩れたりしないように注意が必要です。
もし、冷蔵や冷凍が必要な品物であれば、速やかに適切な方法で保存しましょう。
お礼の言葉を重ねて
手土産をいただいた後、改めてお礼の気持ちを伝えると、より丁寧な印象になります。
直接お礼を言える機会があれば、改めて感謝の言葉を伝えましょう。
別れ際に、「今日は素敵なお土産をありがとうございました」と再度伝えるのも良いでしょう。



後日、電話やメール、手紙などでお礼状を送るのも、より丁寧なマナーです。
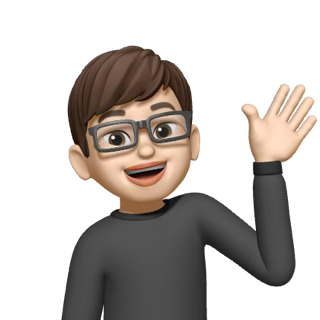
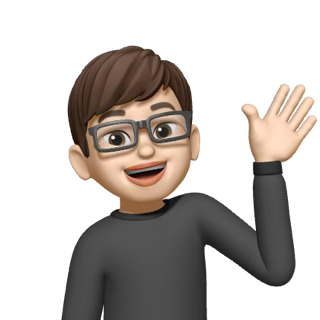

特に、高価なものや特別なものをいただいた場合は、お礼状を送るのが望ましいとされています。
こんな時どうする?手土産Q&A
Q1. 相手に気を遣わせずに、さりげなく手土産を渡したいのですが…
A1. 大げさにならないよう、「たいしたものではないのですが」「お近づきのしるしに」といった言葉と共に、相手がリラックスしているタイミングで渡しましょう。高価すぎるものを避けるのもポイントです。また、「お返しはどうかお気遣いなく」と一言添えるのも良いでしょう。
Q2. 大人数に配る場合の手土産の渡し方は?
A2. 個包装になっていて分けやすいものを選び、代表者の方に「皆様でどうぞお召し上がりください」と伝えて渡すのがスマートです。可能であれば、休憩スペースなどに置いて「ご自由にお取りください」とアナウンスするのも良いでしょう。
Q3. うっかり手土産を渡すのを忘れてしまった!どうすればいい?
A3. 訪問中に気づいた場合は、帰り際などタイミングを見計らって「大変失礼いたしました、こちらをお渡しするのを忘れておりました」と正直に伝えて渡しましょう。帰宅後に気づいた場合は、後日改めてお詫びと共に郵送するか、次に会う機会にお渡しします。その際も、「先日はうっかりしており申し訳ありませんでした」と一言添えましょう。
Q4. 相手が手土産を辞退された場合は?
A4. 相手が固辞される場合は、無理強いするのは避けましょう。「そうですか、ではまたの機会にさせていただきます」と引き下がるのがマナーです。ただし、一度は「いえいえ、ほんの気持ちですので」と勧めてみるのは問題ありません。それでも辞退されたら、素直に受け入れましょう。
まとめ


手土産は、単なる「モノ」ではなく、相手への感謝や敬意、思いやりを伝えるための大切なコミュニケーションツールです。
品物選びはもちろんのこと、渡すタイミングや所作、添える一言に心を配ることで、あなたの気持ちはより深く、そして温かく相手に伝わるはずです。
最初は少し難しく感じるかもしれませんが、大切なのは「相手を思う気持ち」。
この記事でご紹介したマナーやフレーズを参考に、あなたらしい心のこもった手土産の渡し方を実践してみてください。
スマートな手土産のコミュニケーションが、あなたと大切な人との関係をより豊かに、そして温かいものにしてくれることを願っています。










コメント