「ねぇ、スマホ買って!」「〇〇くんも持ってるんだよ!」
子育て中の皆さんなら、一度は(あるいは何度も)お子さんからこんな風におねだりされた経験があるのではないでしょうか?
わが家も、ついにその時がやってきました。
正直なところ、不安でいっぱいです。
…いや、不安しかありません。
簡単に「はい、どうぞ」と渡せるものではない、というのは多くのご家庭で共通の悩みだと思います。
それでも、わが家は最終的に、子どもにスマートフォンを持たせることを決断しました。
今回は、私たちがなぜその決断に至ったのか、その理由と背景をお話ししたいと思います。
わが家がスマホを持たせることに決めた「わけ」
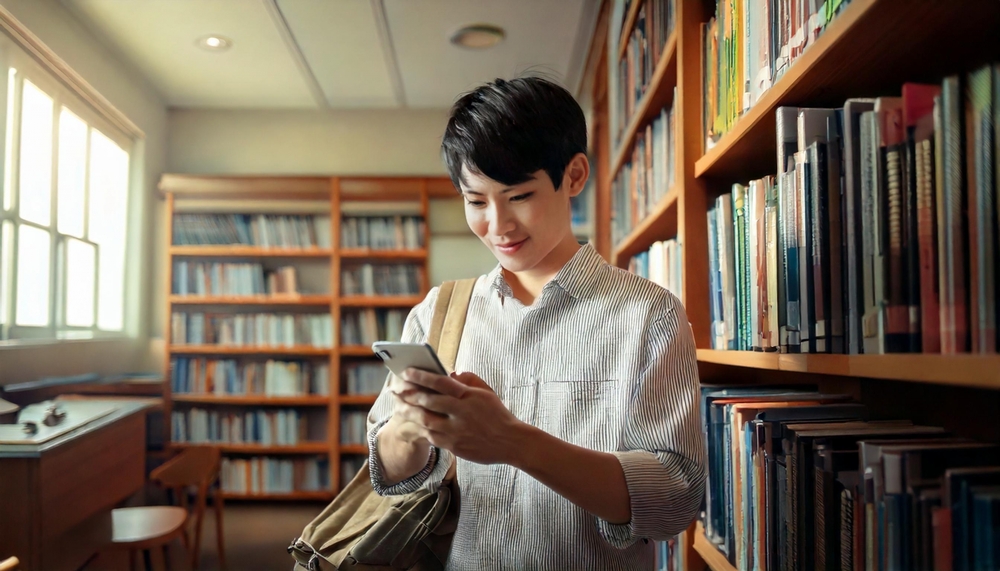
いくつかの理由がありますが、主に以下の点が決め手となりました。
連絡手段としての必要性
子どもが成長し、行動範囲が広がってきたことが一番の理由です。
塾や習い事の帰り、友達と遊びに行くときなど、親と直接連絡が取れる手段があることは、親子双方にとって大きな安心材料になります。
「今どこにいるの?」「何時に帰る?」といった基本的な連絡はもちろん、万が一の災害時や緊急時の連絡手段としても、スマホは重要な役割を果たすと考えました。
友達とのコミュニケーション
悲しいかな、現代の子どもたちにとって、スマートフォンは必須のコミュニケーションツールです。
クラスの連絡網がLINEグループで回ってきたり、友達同士の会話についていけなくなったり…。
「仲間外れになってしまうのでは?」という不安も、無視することはできませんでした。
もちろん、それが全てではありませんが、子どもの社会性を育む上で、ある程度は周りに合わせる必要性も感じました。
情報収集と学習ツールとして
スマホは、使い方によってはかなり強力な学習ツールにもなります。
分からないことをすぐに調べたり、学習アプリを活用したり、ニュースに触れたりすることもできます。
「危険なもの」として遠ざけるだけでなく、正しい使い方を教えながら、情報リテラシーを身につけさせる良い機会だと思うことにしました。
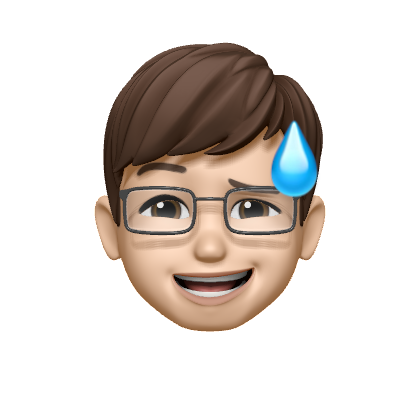
無理くり感が否めませんが、子供へスマホを持たせるための覚悟と言いますか、自分を納得させるための言い訳ですね。
「中高生はスマホなんて無くたって生きていけるのに」というのが本音です。
でも周りがみんな持っているんでね…。
難しいですよね…。
「隠れて使う」より「ルールを決めて使う」


「ダメ」と禁止すればするほど、子どもは親の目を盗んで使いたくなるものです。
友達のスマホを借りたり、隠れて使ったりするようになるくらいなら、最初から家庭内でルールをしっかり決めた上で、堂々と使わせた方が管理しやすいと考えました。
決断と同時に「ルール作り」を徹底
もちろん、ただスマホを買い与えたわけではありません。
決断と同時に、家族で話し合い、以下のような「わが家のスマホルール」を設けました。
利用時間の制限
「平日は夜9時まで」「休日は10時間まで」など具体的な時間を設定。
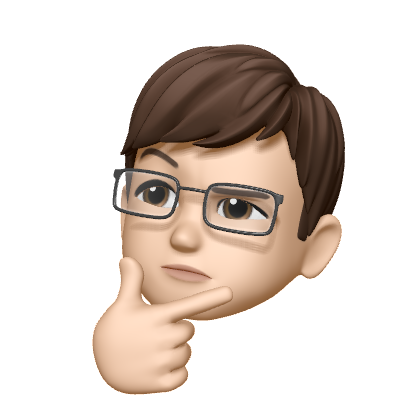
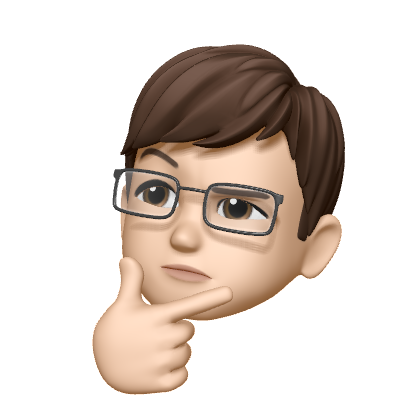

なんか子供の頃、ファミコンでもこんなルール作っていたような。
利用場所の制限
食事中や自分の部屋への持ち込みは禁止。
リビングなど親の目が届く場所で使う。
フィルタリング設定
有害サイトへのアクセスを制限するフィルタリングは必須。
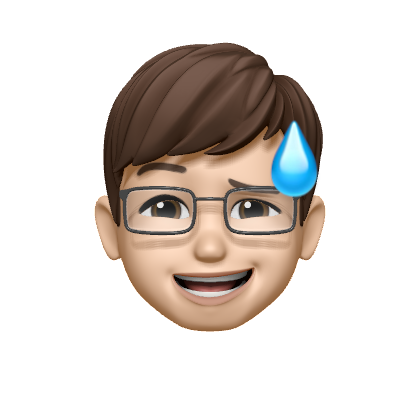
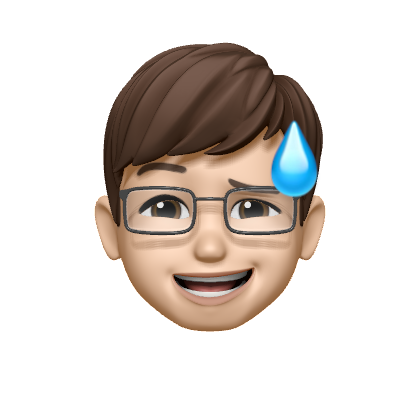

自分が子供だったら「ざけんな」って思うけど、いたしかたないですね。
アプリインストールのルール
新しいアプリを入れるときは必ず親に相談する。
課金は原則禁止(友達づきあいもあるので、一応許可制です)。
個人情報の取り扱い
名前や住所、学校名などをネット上に書き込まない、知らない人と繋がらないことを徹底。
困ったときの相談
ネット上で嫌なことや怖いことがあったら、すぐに親に相談する約束。
このルールは、子どもの成長や状況に合わせて、今後も見直していくつもりです。
ルールを守らなかったときは?


中学生のお子さんがスマホのルールを守らなかった場合、どのように対応するかは、ご家庭のルールや状況によって様々です。
しかし、一般的に考えられる対応と、その際の注意点をいくつかご紹介します。
考えられる対応
まずは話し合い
なぜルールを守れなかったのか、お子さんの言い分をじっくり聞いてあげましょう。
反省している様子が見られるか、ルールを理解していなかった可能性はないかなどを確認します。
感情的に叱るのではなく、冷静に話し合うことが大切です。
ルールの再確認
守るべきルールを改めて明確に伝え、なぜそのルールが必要なのかを理解させることが重要です。
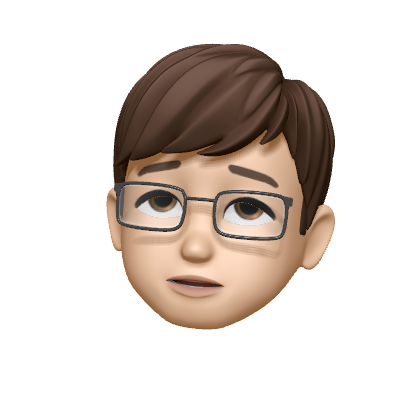
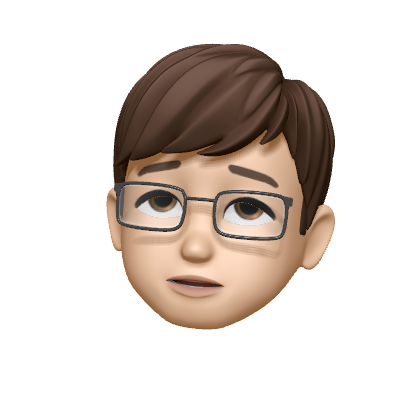

すべてはあなたを守るためなのよ。
段階的なペナルティ
軽い注意・口頭での指導
初めてルールを破った場合や、軽微な違反の場合に行います。
利用時間の短縮
一定期間、スマホの利用時間を短くします。
利用できる機能の制限
アプリの利用を制限したり、特定のサイトへのアクセスを禁止したりします。
一時的な利用停止
一定期間、スマホの利用を完全に停止します。
親がスマホを預かる
どうしてもルールを守れない場合に、親が一時的にスマホを預かります。
原因の究明と対策
ルールを破った原因を探り、再発防止のための対策を一緒に考えましょう。
例えば、時間管理が苦手な場合は、タイマーアプリの導入などを検討します。
ルール見直し
作成したルールが現状に合っていない可能性もあります。
お子さんの成長や生活状況に合わせて、ルールを見直すことも検討しましょう。
家族会議
必要であれば、家族全員で話し合い、共通の認識を持つことも有効です。
対応する際の注意点
感情的に叱らない
頭ごなしに叱ったり、人格を否定するような言葉は避けましょう。
反発心を招き、親子の信頼関係を損なう可能性があります。
一貫性のある対応
その時々の気分で対応を変えるのではなく、事前に決めたルールに基づいて一貫した対応を心がけましょう。
ルールを守れた時は褒める
ルールを守れた時にはきちんと褒め、お子さんの努力を認めましょう。
親も模範となる
親自身もスマホの使い方を見直し、お子さんの模範となるように心がけましょう。
こちらもダラダラとスマホ見るのはやめましょう。
安全確保を最優先に
ルール違反の内容によっては、いじめや不適切なサイトへのアクセスなど、お子さんの安全に関わる場合もあります。
そのような場合は、厳しく対応する必要があります。
専門家への相談も検討
どうしても対応に困る場合は、学校の先生やカウンセラーなど、専門家に相談することも視野に入れましょう。
重要なこと
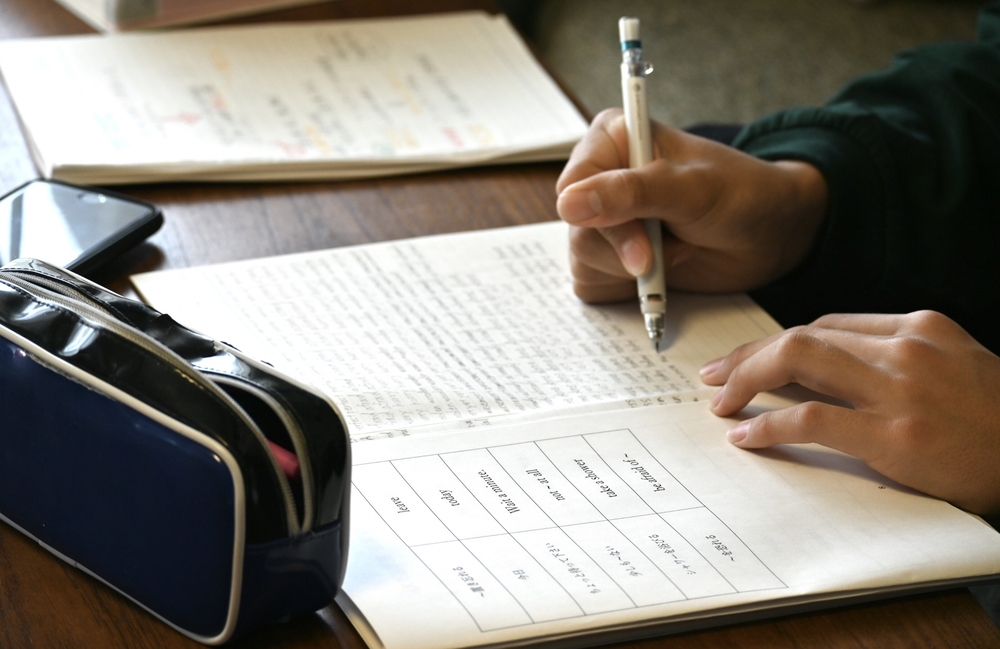

スマホのルール作りは、お子さんの成長に合わせて変化していくものです。
一方的にルールを押し付けるのではなく、お子さんと対話しながら、お互いが納得できるルールを作っていくことが大切です。
ルールを守ることで、スマホをより安全に、そして有効活用できることを理解させることが重要です。
まとめ


子どもにスマホを持たせるかどうかは、本当に悩ましい問題です。
各ご家庭の教育方針、お子さんの年齢や性格、地域の状況によって、ベストな答えは異なります。
わが家の場合、「連絡手段」「友達付き合い」「学習」「管理のしやすさ」といった点を考慮し、厳格なルール作りとセットでスマホを持たせる道を選びました。
これが正解かどうかは、まだ分かりません。
しかし、親子でコミュニケーションを取りながら、スマホと上手に付き合っていく方法を一緒に学んでいきたいと思っています。
もし今、同じように悩んでいる方がいらっしゃれば、わが家の経験が少しでも参考になれば幸いです。
一番大切なのは、ご家庭でしっかり話し合い、納得のいく結論を出すことだと思います。





コメント